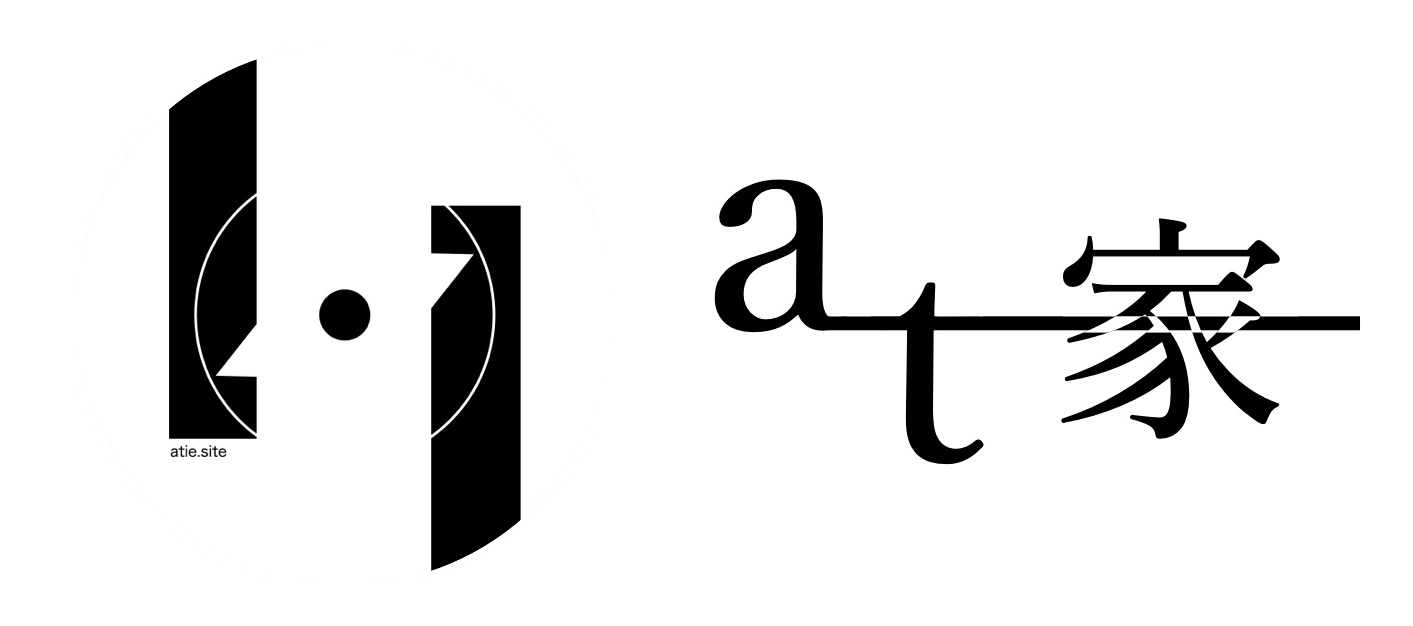COVID-19による影響が私たちの生活を大きく揺さぶる中、美術業界にはどのような変化が起こっているのでしょうか。この取材シリーズ「時代の分岐点;covid-19とこれからの美術」は、様々なギャラリスト、アーティスト、キュレーター、美術関係者に取材をし、これからの美術はどうなっていくのかを様々な視点からお話ししていただきます。
第三回のゲストは、服部浩之氏にお話いただきました。
(取材日:2020.8.19)
-これまでどのような立ち位置で美術と関わって来られたのでしょうか?
服部:アーティスト・イン・レジデンスなどを主な事業とするアートセンターの学芸員として約10年働き、それと並行しながら国際展や芸術祭などの企画運営に携わってきました。また、この数年は美術大学で教員をしながら様々なプロジェクトを実践しています。どちらかというと、若手や周縁的な活動を展開するアーティストの創作活動に関わる機会が多いと思います。アーティストとある程度の長い時間を共有しながら、様々な人やものが混在する場を築く。そんなことに取り組んできました。
この仕事に行き着いたきっかけのひとつは、大学院時代に留学したバルセロナでのアートセンターとの出会いにあります。美術だけでなく、音楽や演劇、ダンス、あるいは映画など様々なジャンルが展開され、無料だったり低価格で刺激的なプログラムに出会える。バーもあって、飲んだりダラダラしたりもできる。そんな多様な人を受け入れる場としてのアートセンターに魅力を感じました。こういう場所が生活のなかにあるのはいいなと思い、結果的にアートセンターで働くようになりました。
一方で、当時バルセロナの旧市街は大きな開発が進み、移民の人々が住む場所を失うなど、混沌として魅力あふれる街区が整備によって消えていく状況もありました。同じようなことは東京でも六本木などの再開発で起こっていました。都市の混沌(カオス)を肯定できる場がアートセンターでもあるということも、この当時実感したんですね。
-街の中にあるカオスさは確かに興味深いものではありますね。非常事態宣言が出されてからの生活の中で何か変化や気付きはありましたか?
服部:オンラインでの情報を追うことが少なくなりました。
もともとSNSをそれほどやっていたわけではないのですが、この状況になってからさらに見なくなりました。もちろん最低限の情報は得ています。
その代わりに、散歩をする時間が増え、ゆっくりと身のまわりの風景の変化を実感するようになり、身近なものへの解像度が格段に上がったと思います。
また、愛知と秋田という離れたふたつの地を拠点としているため、飛行機や新幹線を用いた大きな移動が多かったのですが、そういう移動が劇的に減りました。ひどい時は週4日以上飛行機に乗ることがあって、自分でも異常だなと思うことも多々あったのですが、止まることもできずにいました。それが強制的に止められたことは、ショッキングなことでもあり、同時に不謹慎かもしれないですが少しほっとした部分もありました。現代美術は人や物の移動を前提に成立している産業だと思いますが、その移動が止められたことは、自分の活動そのものを考え直すことにもつながりました。
-日常の中での変化は確かに全てがストップした今だからこそ改めて感じることができるものですね。では、これから生まれてくるアーティストやコンセプトの姿勢にはどのような変化がもたらされると考えていますか?
服部:一概には言えませんが、考える時間は確実に生まれていると思います。
これまで、どんどん生産されること、実践が重ねられていくことや各地で様々なイベントが起こることはよいことと考えられていましたよね。当然様々な動きがあるのは重要ですが、より早く、より多くというあり方は再考されるべき部分もあると思いますし、一度止まって熟慮してから実行に移すという慎重さも大事にされるべきだなと。
これまで、オリンピックなどに向けてたくさんのことを「とりあえずやろう」という方向に向かっていましたが、感染症によって強制的にこういう動きに大きなブレーキをかけられてしまったことは必ずしも悪いことだけではないと考えています。
同時に、様々な国や地域の人とオンラインで対話を気軽にできるようになりました。コミュニケーションのかたちが多様化し、話ができる人の幅は広くなって、そういうのは貴重なことだと思います。一方で、だからこそ、人と直接会って話をすることのかけがえのなさもすごく実感します。オンラインだとダラダラ話すとかはなかなか容易ではなくて、飲み会でどうでもいいことを話すとか、やっぱり豊かなことだなと思います。飲み会とかに慎重にならなければというのは、辛いことですよね。
いずれにしても動きすぎることができなくなったことにより、考える時間を手にしてしまった人も多いと思います。それによって、徐々に人の考え方や価値観が変わり、新しい発想が生まれる局面にもつながると思います。もちろん、それは医療関係者や、エッセンシャルワーカーの方々などの大きな労働があってのことなので、そういう方々への感謝と敬意は尽きません。ただ、エッセンシャルではないかもしれない私たちのような職能の人間がこういう局面においてなにをすべきか、手にした時間で真剣に考えるべきだと思っています。そういう「余白」を今得ていることを意識的に考えなければですよね。
-なるほど。確かに実行の中に「余白」を作ることはものをさらに高める事において確実に必要ですが、見落とされがちですよね。では、感染症によって来場者数を削減する事にもなってしまった美術館やアートセンターは今後どのような振る舞いが期待されるのでしょうか?
服部:役割分担がクリアになっていくと思います。
近年、美術館もアートセンターも、それこそ芸術祭なども似たような取り組みが多くなりすぎたように思います。それこそ若手のアーティストの発表の場は飛躍的に増えていたました。でも、本来文化施設などは、その性質に応じてそれぞれ異なる得意分野と専門性があるはずです。例えば美術館であればコレクションを再検証し、しっかりと見せて行くことや、資料などのアーカイブを充実させることなどに意識が向かうと思います。一方でアートセンターは、作品などがつくられる、生のものに出会える場であり、生まれることに立ち会える場、そして地域の生活とより近い、多様な学びの場という側面が明確になっていくと思います。巨大でなくてもいい。適正規模で、よく練られ、より手間暇がかけられた丁寧なプログラムが展開されていくことをのぞみます。こういう時代だからこそ、文化や芸術が切実に求められるようになると信じています。
-ありがとうございました。
服部 浩之 Hiroyuki Hattori
キュレーター/秋田公立美術大学大学院准教授。
1978年愛知県生まれ、愛知・秋田拠点。2006年早稲田大学大学院修了(建築学)。2006年~2009年秋吉台国際芸術村、2009年~2015年青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]などで様々なアーティストの制作プロセスに関わる。近年の主な共同企画に「Media/Art Kitchen」(ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、バンコク、青森|2013~2014年)、あいちトリエンナーレ2016(愛知県美術館ほか、愛知|2016年)、「近くへの遠回り」(ウィフレド・ラム現代美術センター、ハバナ|2018年)。第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」キュレーター(2019年)。